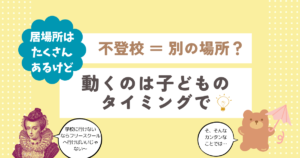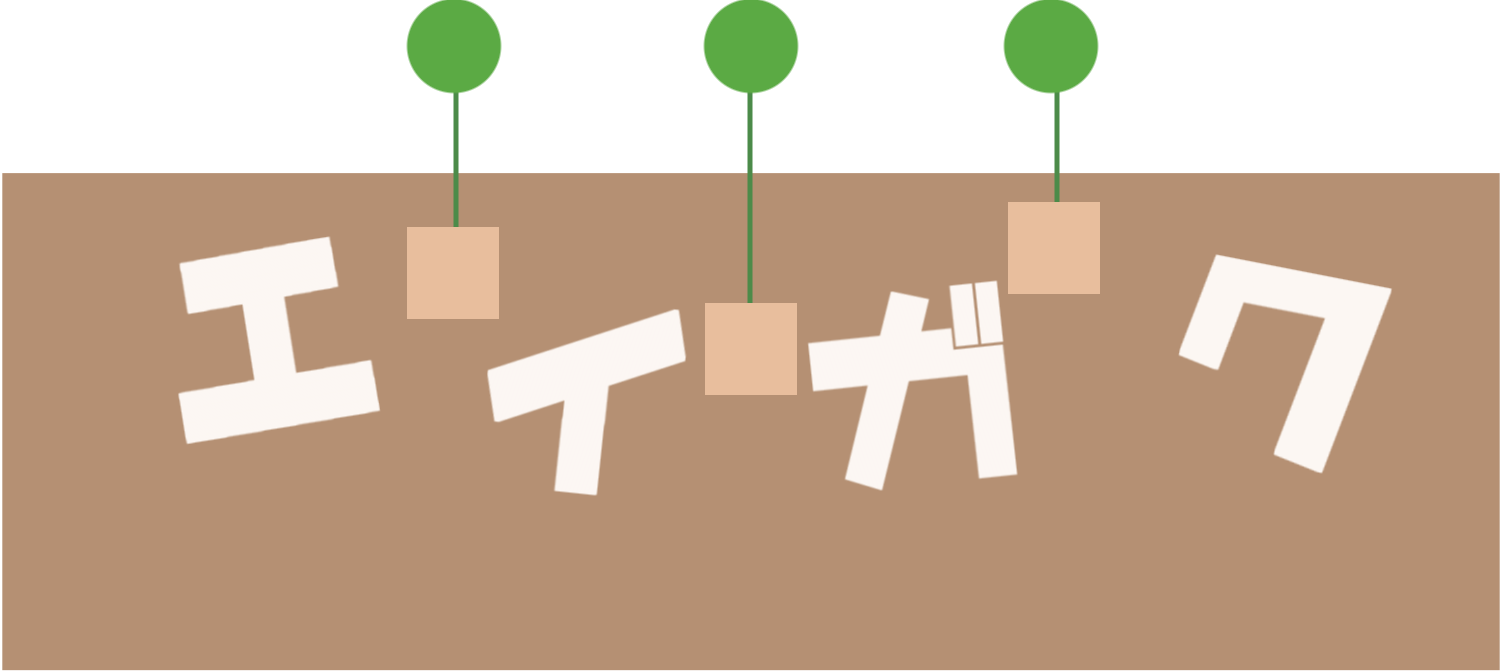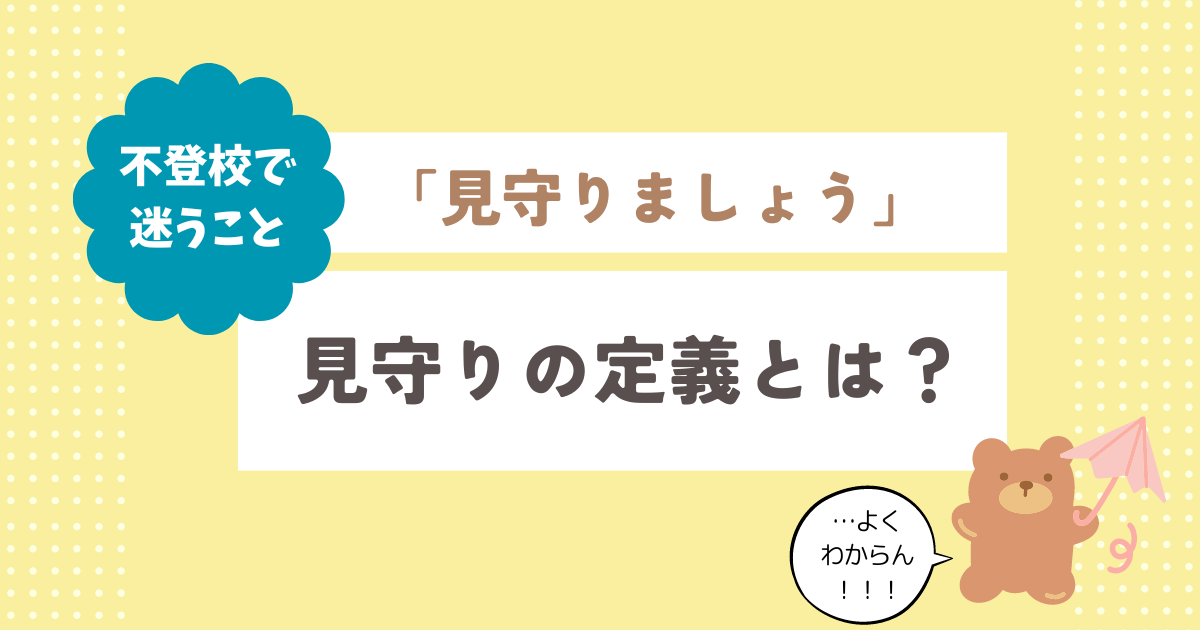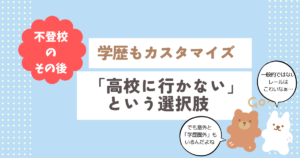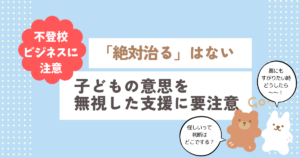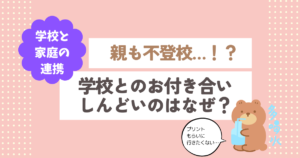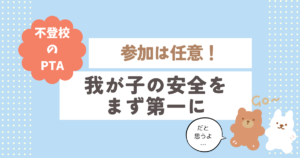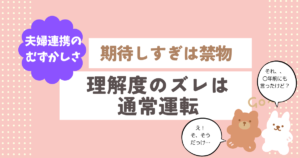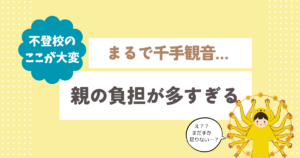子どもが不登校になりずっと家にいる状態は、親にとって大きな負担です。
なかなか動かない子どもに対して、モヤモヤ。
無理して学校行かなくてもいいとは思う、でもゲームばかりでどうしたら…!
そんなお悩みに対して言われがちなアドバイス。
「本人が動きたくなるまで見守りましょう」
見守るって、、どういうこと?
いつまで「見守れば」いいの!?
この記事では、そんな疑問を紐解いていきます。
「見守り」と「放置」はちがう!
分かりやすい例としては、小さな子どもへの見守りがあるでしょう。
例えば、
パートナーに子ども(幼児)任せたら、スマホばかり見ていて子どもの相手は全くしなかった。
一緒にいたのに怪我をさせてしまった。
…なんて事があった方は、イメージしやすいかもしれませんね。
ただ見ている(実際は放置)のか、「見守って」いるのかでは、
行動も声掛けも変わってくるはずです。
その子に興味を持つこと
観察してみること
必要がありそうなら、関わったり、サポートをしたり、共に試行錯誤してみること
近くにいる保護者ができるとしたら、こういう面ではないかと思います。
もちろん子どものタイプや年齢、心身の状態にもよりますので、「どう関わるか」は一人一人が違いますが
違うからこそ、「この子はどうしたいのだろう」「本当はどう感じているのだろう」を意識していくことが、
見守りにつながっていくのではと感じます。
怪我も、擦り傷なら経験した方が良いということもありますが、命に関わる怪我となれば別ですよね。
※動きたくなる時期の見極めは、別途大切になってきます。
余裕をもって見守るためにも、まずは保護者がリラックスする
子どもが不登校になった場合、保護者は余裕がなくなったり、孤独になりがちです。
その中で見守っていくのは疲れますし、緊張や焦りや比較で辛いことも多々あるでしょう。
なるべく冷静に、フラットにして情報を得ていくことが大切ですが、
最初は子どもと同化したり、不安や怒り、悲しみの感情が先に来てしまうかもしれません。
できるだけ早い段階で第三者や相談できる場に繋がってほしいと感じますが、
まず共感してほしい!悲しみや怒りが強い!場合には、
同じ立場の保護者であったり(当事者会、保護者会)、
カウンセラーさんに話を聴いてもらうと、心が整理されやすいことがあります。
子どもに一番近く、子どもが安心しやすい、心を開きやすい存在が保護者だからこそ
早めに落ち着きを取り戻し、自分らしく判断していけるようなアプローチは大切です。
※正解を探すというより、ご家族にとっての心地よい選択を決めていくことが大切だと私たちは考えます。
相談する事が苦手な方もいらっしゃいますが、恥ずかしいことはありません。
感情がフラットになってからは、相談先や支援者からの情報が受取りやすくなり、また判断しやすくなります。
なお第三者は、「他人だからこそ」共感しすぎずに言えることもありますので、
どんな選択肢があるのかなどの情報を「参考に」聞けるとよいでしょう。
「見守り」ができると、学校へ行く・行かないに囚われなくなる
近くにいる大人、周りにいる大人が落ち着いて考えていけるようになると、子どもの姿を評価せず、まっすぐ見ていくことができます。
そうすると、日々の些細な喜びを分かち合えるはずです。
「なぜ自分は、子どもに学校へ行ってほしいと思っていたのだろう?」など、理由を深く問うようになる段階で、もう行く行かないの考えからは解放されているはずです。
今本当に必要なのは何かがわかるようになることは、今後の生きやすさの土台に繋がっていくはずです。
最初は苦しい日々があり、どうしても何かにすがりたい時期もあるかもしれませんが
価値観は時間や経験の積み重ねとともに、自然と変わってゆくものです。
焦る時ほどうまく周りに吐き出しつつ、客観的になれる時間を持てるとよいでしょう。
子どもを心配することは、自然なこと。遠慮なく見守ってほしい理由。
最近では、「自分は子どもを信じているから、手助けは不要なんだ」と極端に考える人もいるようです。
もちろん、信じることは必要ですし、過保護な手助けは子どもの成長に影響を及ぼすことですが
極端な選択こそ、「放置」になっていることもあります。
また、子どもを信じるということは、「困っていても手を貸さない」ではないはずです。
子どもが今、何が必要で必要じゃないのか、それは大人が決めることではありません。
子どもは言語化が苦手でわかりにくいかもしれませんが、配慮が必要なことも実はたくさんあります。
視力の低い子に「自力で見れるようになるはず、信じてる!」とは誰も言いませんよね。
知らないうちに困っている、困っていることにすら気づけていない
そんな可能性も考えながら、大人がなるべく余裕を持って見守っていけるとよいですね。
関連記事▼