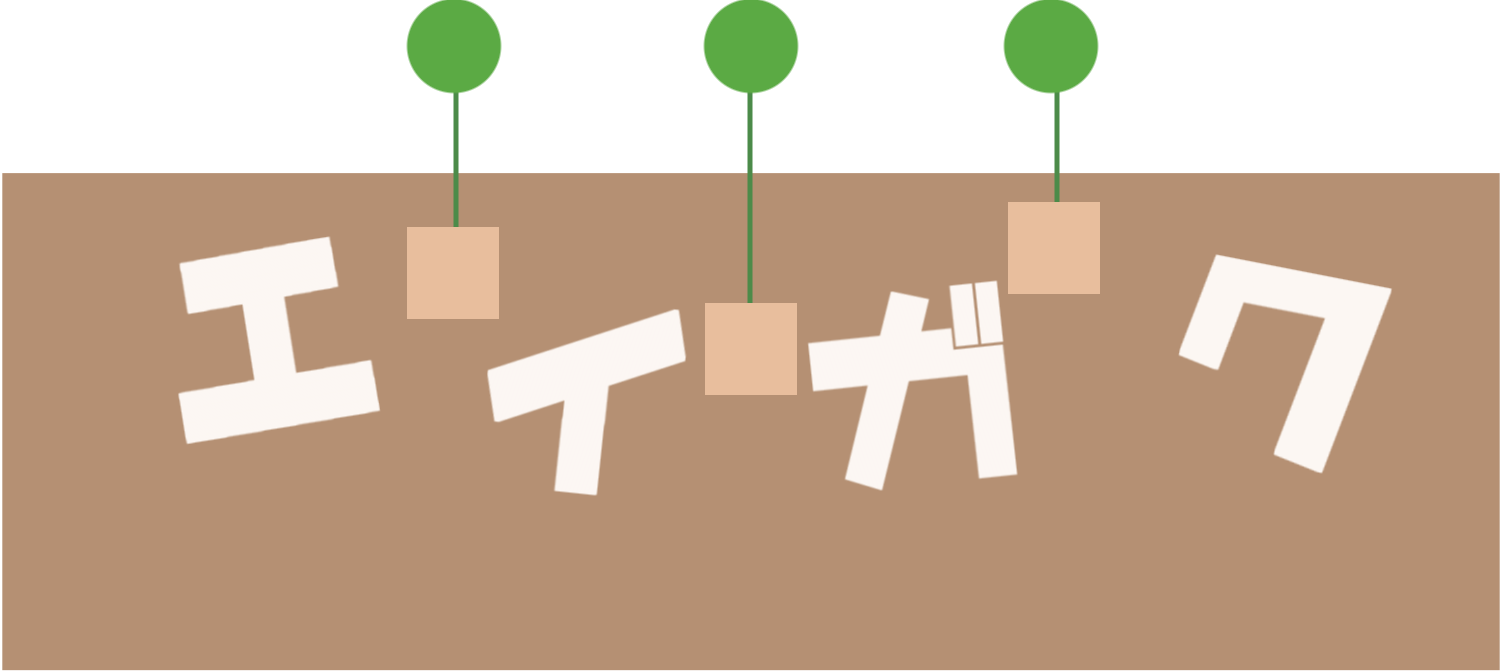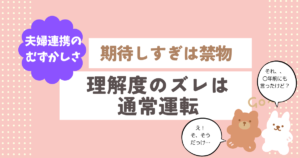1. はじめに 〜なぜ今、海外教育なのか〜
日本の教育って、いつからこんなに「詰め込み」と「枠にはめる」ことばかりに力が注がれるようになったんだろう。もちろん一律の基礎教育は必要だ。でも、子どもたちが本来持っている「自分で考える力」や「ことばにできない気づき」が、まるで“扱いにくいもの”のようにスルーされてしまう場面を何度も見てきた。
たとえば、ロジカルに考え、仮説を立て、異なる視点から再構築しようとする子。学校の中では“屁理屈っぽい子”と見なされることがある。一方で、表面的な正解を「暗記」して言える子が評価される。
だけど、社会に出たときに必要なのは本当に後者だろうか?
こうした違和感の積み重ねのなかで、私は「じゃあ他の国はどうしてるんだろう」と思い、海外の教育に注目するようになった。
2. 日本の教育の構造的な問題
もちろん、日本の教育にも良い面はある。世界的に見ても読み書き計算の基礎力は高いし、努力することの価値を教える文化もある。
でも、「考える力」や「問いを立てる力」がカリキュラムの中で優先されていない。
受験や資格をゴールにする風潮があまりにも強く、“思考のプロセス”よりも“答え合わせの速さ”が評価されてしまう。その中で、「このままでは学ぶ意味がわからない」と感じて離脱していく子どもたちがいる。不登校になるのは、その子が弱いからでも、やる気がないからでもない。
「枠」に合わないこと、それだけで学びから排除されてしまう構造がある。
学び直す場所がないという現実
たとえば学校を離れた子に、「別の形で学び直せる場」があればいい。でも、日本では「制度から外れた子」が安心して学べる選択肢が少なすぎる。自治体や制度による支援は増えてきたけれど、それでもやっぱり“学校復帰”が前提にされがちだ。
大学院や専門機関も、基本的には「就職につながる」ルートを強く意識している。学びそのものを深める、という動機は後回しにされやすい。その結果、たとえば哲学・言語学・教育学といった「問い続ける力」が求められる分野は、表に出にくくなっている。
では海外はどうか? ロジカルを育てる学び
海外のすべてが優れているわけではないけれど、「考えることが前提」の教育設計はやはり一歩進んでいると感じる。
たとえばPBL(Project-Based Learning)が本当に機能している事例では、答えを導く力よりも、「問いを立てるセンス」や「プロセスの納得感」に重きが置かれている。
そしてこれは、特別な子に与えられるものではなく、むしろ「多様なバックグラウンドを持つ子どもたち」のために用意されている。
移民が多い国や、家庭内言語と学校言語が違う環境では、“翻訳しながら理解する力”や“言葉を超えて考える力”が教育の中核になる。
そう、これこそが私が英語を通じて提供したい「学びの型」のひとつでもある。
英語を教えたいわけじゃない、「英語で学ぶ意味」がある
だからこそ、私が目指す講座では、「英語を教えたい」わけではない。
英語はあくまで“概念を運ぶ道具”だ。
たとえば算数の問題を英語で解くとき、そこには単に語彙や文法を使う以上の「分解」「構造化」「翻訳」「再統合」のプロセスが生まれる。
これがまさに「ロジカルシンキング」や「クリティカルシンキング」のトレーニングになる。
しかも、“英語だからこそ”腑に落ちる瞬間がある。
日本語で「順番を考えよう」と言われると、なんとなくフワッとしてしまう子が、「First, then, finally」という構造に触れることで、物事の組み立てに気づく。
英語を通じて学ぶとは、そういう意味での“別の地図を手に入れる”ことでもある。
日本にいながら海外型の教育を受けるという選択
海外の教育は良い。でも、実際に移住するのは現実的じゃない。
だから、日本にいながら「思想」としての海外教育に触れられる仕組みが必要だと思った。
そしてそれは、英語力や学歴とはあまり関係がない。
むしろ、「どうやって教えるか」「どう学びを構造化するか」に面白さを見いだせる大人が関わることで成り立つ。
私はこの学びを、押しつけのない方法で届けたい。
「これが正解だ」とは言わない。ただ、今の教育の枠組みに違和感を持っている人にとって、「こんな学び方もある」という選択肢を見せたい。
そしてそれが、遠くでくすぶっていた子どもの学びに火をつけることがあるなら、本望だと思っている。
おわりに:教育の未来を手渡す人をふやしたい
子どもが「自分で考えることをやめない社会」にしたい。
そのためには、まず大人が「問いを持ち続けること」を手放さないことが大事だと思う。
この講座は、そんな大人たちに向けた一つの「武器」だ。
英語をツールに、思考と言語と教育をつなぎなおす。
それは、日本の教育の外側から、内側を少しずつ揺さぶるような行為かもしれない。
そんな仲間が、少しずつ増えていくことを願っている。